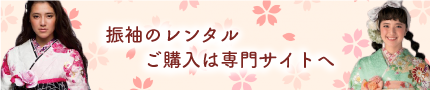blog
社長、本場結城紬を訪ねて結城市へ
2021年8月2日
みなさま、こんにちは!
今回は社長の工房見学のレポートをお届けいたします。結城紬を求めて茨城県結城市へ行って参りました。
今年、本場結城紬はユネスコ無形文化遺産に登録されて10周年を迎えました。それより以前に昭和31年には国の重要無形文化財になっています。
結城紬の最大の特徴はその糸にあります。普通、蚕が作った繭のいくつかから糸を引き出し撚って一本の絹糸になります。結城紬の糸は一つの繭から真綿を作りそこから糸を引き出し紡いでいきます。
糸作りの他にも絣括りと、居座り機で織られることと、この3点の特徴が無形文化財の指定を受けています。
そんな本場結城紬の産地へ、いつもお世話になっています外与株式会社の笹田さんにご案内いただきました。お世話になりました。
まずは結城市伝統工芸館へ。ここでは糸を紡いでいるところ、居座り機で反物を織っているところを見学させていただきました。

こちらが糸を紡いでいるところです。真綿をつくしという道具に巻き付けて細く均等に引き出していきます。

1反分の糸はなんと35㎞の長さになるそうで、その気の遠くなる作業に社長も驚きです。

こちらが居座り機です。結城紬は緯糸の打ち込みがとても強く、1㎝の長さの中に100本の緯糸が織られているのだそうです。数ミリごとに手で緯糸の調整をします。


結城紬は奈良時代には朝廷に献上され正倉院にも収蔵されています。最近小山市で機織りをしている埴輪が発掘されたのだそうです。この地域は2000年前から織物が盛んだったと言われています。こちら埴輪の復元だそうです。

次は湯通し工場へ。結城紬は糸が細く柔らかいため糸の段階で糊付けを行います。染めや絣作りの後など最低3回の糊付けが行われているそうで、仕立てる前にはその糊を落とす作業をしなければなりません。その糊の量は一反一反違うため、職人さんが反物の状態を見て手仕事で糊を落としていくのだそうです。

湯通しの後はこのように乾燥させます。真綿で撚りをかけていない糸で織られた結城紬は乾いて空気を含むとふわっと上に膨らむのだそうです。

本場結城紬は重要無形文化財の指定を受けていますが、一部効率化したものを結城紬 はたおり娘として奥順さんがオリジナルブランドとして提案されています。奥順さんは明治40年創業の結城紬最大の産地問屋です。
効率化と言っても本場結城紬と変わらない手間と手作業に社長もとても驚いていました。
糸はつくしを使った手紡ぎではありませんが手紡機という道具を使った真綿から紡ぎ出された糸ですし、絣も全て手で括ります。



機織りは居座り機では無く動力を使っているものの、やはり数センチごとに手作業で緯糸を整えていかねばならず、手間はかなりかかります。今まで動力に耐えるために経糸は生糸を使っていると思っていましたが、細い生糸に手紡糸を絡めた糸を使っているそうで、経糸緯糸共に真綿から作られた糸なのだそうです。


はたおり娘の工房、小野織物さんのご主人と。

そして、奥順さんが創業100周年を記念して作られたつむぎの館へ。貴重な文献や道具が展示してある資料館では奥順株式会社の会長が案内してくださいました。


これは真綿をひっぱってのばしたところです。とても大きくなります。

結城紬の製品も置いてあります。モダンな絣模様です。無地もおしゃれです。無地と言っても先染めの織物です。


こちらは奥順さんの社長です。8月に開催します結城紬の個展では奥順さんにご協力いただきます。

そして翌日は染めの工房へ。
結城紬の糸は糊をつけているので染まりにくく、「たたき染め」という染め方で染めるのだそうです。結城紬独特の染め方でびたびたんとたたきつけて染めます。


渡辺紺屋さんにて。

紬が大好きな社長も知らなかったことや、驚き感動したことがたくさんありました。この感動をたくさんの方にお伝えして結城紬の素晴らしさを体感していただきたいときもの館で個展を開催いたします。その成功を祈願して大桑神社もお参りしてまいりました。大桑神社は養蚕・織物の神を祭神とした神社だそうです。


結城紬も年々生産反数が減り続けている織物です。実は結城紬の産地は東京から約80キロという都心に近いところにあります。結城紬に携わっている方は平日は他の仕事をしながら作業を続けこの伝統技術を継承されています。私たちもこの結城紬の魅力を多くの方に知っていただき、産地復興の一部になれたらと思っております。
8月20日からの四日間、きもの館で催されます「楽笑会」へ皆さまぜひお越しくださいませ!