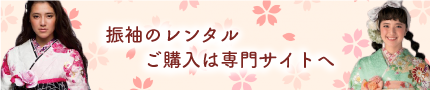blog
小紋屋高田勝さん 栗山工房さんへ社員研修
2016年11月6日
みなさま、こんにちは!
今回はお久しぶりの番外編です。先日、社員研修として京都へ工房見学に行ってまいりました。本きもの松葉では社員研修を年間100時間以上実施しています。新人さんやパートさん、チーフ、店長などとそれぞれに応じた研修を受けて頂き、お客様により良いサービスを提供できるよう勉強してもらいます。今回は経験を重ねてもらっている18名の社員さんが参加です。研修の様子を二回に分けてご紹介したいと思います。
私はきもの館、古市店、ロゼ店、泉が丘店の社員さんと金澤部長の運転する10人乗りの車で一緒に連れて行ってもらいました。
車の中はとっても賑やかです。遠足気分を通り越して宴会気分です。どんな時でも最大級に楽しむうちの社員さんは本当に頼もしいです。写真が逆光で、しかも運転中に撮ったのでブレブレですが逆にその方が良いかもです。ふふ。
たくさんの美女たちを乗せて責任重大な金澤部長です。めっちゃ笑ってますけど。
集合はいつもお世話になっていますみつわ商事さんの会社です。展示会でお客様からの信頼の厚い硬派な奥川さんです。今日は一日お世話になります。
みんな揃いまして金澤部長と奥川さんからご挨拶を頂き、早速歩いて高田勝さんへ向かいます。
小紋屋高田勝さんはたくさんの映画やドラマなどに衣装提供されています。どれもとても有名な映画や番組で、しかもすごい本数ですのでほとんどの方が目にしているのではないかと思います。今日は小紋についての講義を受けた後、実際に店舗で販売する高田勝さんの小紋のお柄を選品させて頂くことになっています。
早速小紋についての講義を受けます。こちらが高田社長です。選品もしなければいけない上に、この後栗山工房さんへ見学に行かなければいけないので短い時間でしたがぴたりと時間内にお話頂いてとってもびっくり。お話はとてもテンポよくわかりやすく短い時間しかお話し頂けなかったのがとても残念でした。
みんなメモを取りながら聞きます。
小紋は色々なお柄を繰り返し型染したものです。そのお柄は小さいものも大きいものも様々です。でももともとは小さいお柄の型染で、いまの江戸小紋のような細かい柄の着物を小紋といったのだそうです。
小紋と言えば普段着、洒落着という認識ですが、昔の着用範囲は今の附下ぐらいまでだったそうです。そして「訪問着」というのは大正時代に、「附下」というのは戦後にできた着物の種類なのだそうです。そういえば昔は小紋に紋付の羽織を羽織って正装にしたとどこかで見たことがあります。入学式や卒業式など、黒の紋付の羽織を着て写真に写っています。着物が日常着であった時代はもっと柔軟にTPOに合わせることができたのでしょう。衣替えも同じく、「6月9月は単衣、7月8月は薄物、それ以外の月は袷」という衣替えのルールを着物入門の時によく聞きますが、本来衣替えの習慣というものはなかったのだそうです。今、このルールをきっちり守っているのは花街ぐらいなのだそうで、気候や着る環境に合わせて単衣、袷を選ぶ方が主流となってきています。「着物はルールが色々あって堅苦しいから嫌」というイメージを持たれる方も多いように感じますが、もともとの着物の着こなしから時代と共に変わってきている衣服の習慣などを勉強して、お客様に納得して楽しんで頂ける着物のご提案ができるようになればいいなと改めて思いました。
そして、今回は和染紅型の栗山工房さんへ行くということで染についてのお話が中心です。また次回の栗山工房さんについて書くときに染のこともご紹介しますが、高田勝さんのこだわりの小紋を見せて頂きながら染の技法について色々と教わりました。よく裏まで染料が浸みていると手描きでいいものと言ったりしますが一概にそういうわけではないそうです。型紙を置いて繰り返し手作業で染めていくやり方とロール状の型紙で一気に反物を染めていくやり方と、どちらも一長一短の特徴がありデザインやこだわりに応じて使い分けているそうです。染の過程で無くてはならない防染糊の難しさ、その「染まらないところ」をどうするのか、隣の色と混じらない技術、色々なお話を聞いて繰り返し柄の小紋をなんとなく簡単に思っていたことに申し訳なく思いました。産地によって作り方も風合いも違う紬と同じように、小紋もお柄によって使う型紙の数、染めの技法、白生地の種類も上げれば本当に様々なこだわりがあります。お柄も一つ一つに意味があったり作り手さんの思いが込められていたり、もう無限の魅力があります。今回店舗の方で高田勝さんの小紋を置かせていただくことになりみんなでお柄の選品をしました。どれも素敵で迷ってしまします。
一つ一つ見て選んでいきます。また店頭に並びましたらみんなで選びました高田勝さんの小紋をじっくりとご覧くださいね。
あと少し時間ができましたので高田社長が小紋のコーディネートのお話をしてくださいました。足跡柄の小紋に、犬や猫のお柄の帯を合わせてストーリーのある着こなしをすると楽しいですねと見せて頂きました。
テリアの帯。
こちらは猫ちゃんの帯。
着物の着こなしにはこうした繋がりで楽しんだり、季節感を表したり、または物語や逸話などに絡めてお柄を選んでコーディネートしたりという面白さがあります。着物は洋服とは違い形は同じですが表現できることは洋服よりも深く幅広いのではないかと思います。着物をご提案するときに、希少価値であることや技法の特殊さだけでなく面白さについても感じて頂くことができたら、またさらに皆様のきものライフが楽しいものになるだろうなと思いました。
高田社長はきもの文化検定の実行委員長をされているそうで、ここ数年お勉強が滞っていることにはっと気づき、また来年頑張ってチャレンジしてみようかな~と思ってしまいました。いや、毎年思っているような気がしますけど・・・。来年こそは、子供の受験も終わりますし落ち着いて勉強できるかな。うーん、受験が終わってなかったりして・・・。
また今回も長々と書いてしまいました。次回は栗山工房さんの工房見学について書きたいと思います。