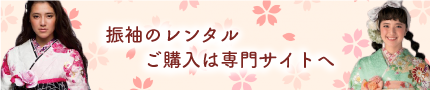blog
べっぴんの会2022での着物
2022年6月22日
みなさま、こんにちは!
べっぴんの会にお越しいただきましたお客様、誠にありがとうございました。
今回のべっぴんの会は、四国から「天然藍灰汁発酵建てによる藍染め」という江戸時代からの伝統技法を今も貫いていらっしゃる矢野藍秀先生にお越しいただき、藍染の様々なお話を披露していただきました。
矢野先生を始め、作家の先生方、問屋さんの皆さま、素晴らしい商品を揃えていただき誠にありがとうございました。
まずは初日、江戸時代に染められた藍の布団地の前で。
着物はしょうざんの単衣に相良刺繍の夏帯です。半衿はただいまエントリー募集中のきもの披露空間(←コチラ)の「いいね!」賞になっているシースルーの半衿です。
藍の葉っぱを手にお話される矢野先生です。藍染めについてのお話を丁寧に教えて下さいました。先生の手の爪も藍で真っ青です。写真手前にかけているのは火消し袢纏です。火消しさんたちが着ていたもので内側が藍の無地の生地で二枚合わせを刺し子のように縫い合わせています。藍は防火作用もあるのですって。
内側はこんな感じ。驚くべきは江戸時代に着ていた藍染は今でも普通に着られるぐらい丈夫で綺麗なことです。天然の藍のパワーは凄いです。
2日目は、久留米絣に夏牛首のしゃれ帯を合わせました。衿は絽の半衿を。久留米絣は木綿の織物です。濃い藍染めに白い絣模様が一般的ですがこれは珍しく淡い色合いの久留米絣です。日本三大絣の一つなのだそうです。
3日目はしょうざんに別の相良刺繍の帯を合わせました。このコーディネートは5月の創業祭のときと同じ(過去記事←コチラ)ですが、今回はより涼し気に帯締め帯揚げは夏物で。単衣は5月から着用しますが小物類は5月は袷のものを、6月から夏物を使うことが多いです。帯も、5月はまだ袷のものを締めることもあります。近頃は軽やかな単衣用の帯というものもあって重宝です。
そして四日目、最終日は久留米絣に三季さんの染めの名古屋帯を。
久留米絣は国の重要無形文化財に認定されているものもあります。認定されるには、手括りによる絣糸を使用すること、純正天然藍で染めること、なげひの手織り織機で織ること、の三つが条件なのだそうです(純正の藍染というのが条件の一つに入っていますね!)。この三つの条件を満たす久留米絣はなかなか無いので貴重です。しかしながら久留米絣は国の伝統的工芸品としての認定も受けていますので伝統工芸品の証紙が貼ってあるものもありますので、また目にする機会があれば見てみて下さい。
本きもの松葉の着物でお出かけの予定も充実してきています!着楽楽きもの教室(←コチラ)の生徒さんも皆さんとても楽しそうにレッスンに通われています。自分で着物を着られるようになると、本当に楽しみが広がります。是非皆さま、気軽に着物の楽しさに触れて下さいね!