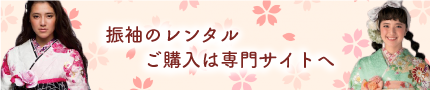blog
絞り染めの着物 竹田庄九郎
2015年9月23日
みなさま、こんにちは!
少しご無沙汰してしてしまいました。シルバーウィークはいいお天気に恵まれまして、ここきもの館では大催事「お楽しみ三昧」を催しておりました。期間中お越しいただきましたお客様、誠にありがとうございました。大催事では多くの問屋さんや作家の先生にお越しいただき会場を盛り上げて頂きました。普段見られない素晴らしい作品をお客様にご覧いただけて嬉しく思っております。本当にありがとうございました。
その中で今回、有松絞りの竹田嘉兵衛商店さんにお越しいただき絞り染めのお話を色々お伺いすることができました。知らないことも多かったので少しご紹介したいと思います。
絞り染めは布に模様を施すものとして日本最古の染色技法なのだそうです。布を糸で括り染めるという単純な方法で、世界中でこの染色方法は見られますが、日本が群を抜いて種類も多く精緻で伝統の技術というにふさわしい素晴らしい技法です。有松絞りは開祖竹田庄九郎により有松の地で400年近い歴史を持ちます。
絞りの着物はとても手間暇がかかるので江戸時代にはしゃし禁止令が出され、人前で着るのをはばかられたことから「絞りの着物は正式な場所、フォーマルには着られない」と誤解されている方もいらっしゃいます。私もなんとなくそんな風に思っていましたが、総絞りの無地は紋を入れなくてもそれだけで紋付の色無地と同じ格のある着物と見なされるのだそうです。皇室でも正式な場所で着る着物、という認識や、古い伝統のあるものが格が高いという認識から絞りの着物も格のあるフォーマルの着物として着ることができます。
そしてこの絞り染めは身を守る厄除けの意味合いもあるそうです。節目のお祝い着にも七五三では被布や鹿の子の髪飾りに、二十歳には豪華なものだと総絞りの振袖や、お柄の中に絞りが入っていたり、帯揚げで取り入れたりと、そういえば絞りがあちこちで使われているのにはそういう意味があったのかととても勉強になりました。
竹田嘉兵衛商店さんの着物はとても生地がしっかりしていて絞りの着物特有の裏打ちをしなくてもいいのだそうです。絞りの着物で敬遠されるのはあのふっくら感と裏打ちとでふくよかに見えるというところです。絞りの生地を伸びないように薄い布で裏打ちをして胴裏を付けるとそれだけで三枚、襟元や腰回りなど着付けて重なるとすごいことになるのですが、竹田さんの着物はとてもすっきりと着ることができます。皇后美智子さまや、紀子妃殿下も竹田嘉兵衛商店さんの着物をご購入されているそうです。
絞り染めはもともと染の技法なのでもっと平たく伸ばすのが本来だったそうで、それが次第にこのふっくらシボがあるのが手括りの証として人気が出るようになったようです。元に戻るのですが、日本の最古の染の技法の「纐纈、夾纈、﨟纈」の中の「纐纈」が絞り染めにあたります。最初は着物の裏地などに施されていたようですが、室町時代に辻が花染めが生まれ絞り染めが表舞台に出てきます。その後細かく繊細な作業で作り上げる総鹿の子の着物は女性たちの憧れとなり非常に高価で贅沢だったため、江戸時代の後半に鹿の子の模様を型紙を用いて摺り染にしたものができました。これが摺匹田です。手括りの総鹿の子と摺匹田と区別するのはやはり生地の凹凸です。でもその後、流行も変わり平面的な質感を持った生地や加飾技法が好まれ、摺匹田もその中の一つとして扱われ、今では手括りの絞り染めの代用品という意味合いではありません。
今回、有松絞りの素晴らしい着物を見せて頂いて色々とお話を聞き、自分でも少しだけですが絞り染めのことを調べてみました。着物に使われる色々な技法もこうして一つ一つ知っていくと着物を着るときにとても嬉しく大切に着ることができます。まだまだ知らないことがいっぱいある上に、聞いてもすぐに忘れていくのですがまたこれからも勉強したいなと思います。