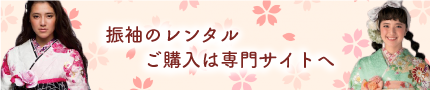blog
藍の文化展でのきもの
2015年9月7日
みなさま、こんにちは!
「藍の文化展」にお越しいただきましたお客様、誠にありがとうございました。
昨年もこの時期に藍の文化展をさせて頂きました。その時のブログ(過去記事←コチラ)にもご紹介しておりますようにこの時期、徳島の秋の風物詩「藍の寝せ込み」が行われます。過去記事で藍のことを述べさせて頂いておりますのでまたご覧いただければと思います。一年ぶりに藍の商品に囲まれてまた感動が蘇り、日本の伝統技術に誇らしさも感じました。
毎年種をまいて藍を育てなければ藍はもちろん、その後の藍のための種も採れないのです。
春に撒いて夏に摘み取った葉をまずは乾燥させます。お茶にして飲めるそうです。本藍染は全て天然素材で出来ているので藍染めの途中で口に入っても大丈夫だそうです。
そして、秋に約100日水をかけながら切り返して発酵させ「蒅すくも」を作ります。これが藍染めの元になるものです。
この蒅を作る藍師は徳島県でただ一軒、佐藤家しかいらっしゃいません。このことも過去記事(←コチラ)に書いてあります。伝統を受け継ぎ守り伝えていくことの大変さをまたしても感じてしまいます。
さて、今回三日間の開催でしたが同じ着物で帯だけ変えて着てみました。9月の初めはもう単衣を着てもいいですし、まだ暑いですので夏物でも大丈夫です。でもお洋服でもそうですが、季節先取りがおしゃれなので暑いからと言ってあまりに盛夏と同じものでもなぁ・・・という感じでしょうか。少し秋の気配を感じるようなものも素敵だと思います。そういう私は何を着ていいのかわからなくてとりあえず透け感の少ない夏牛首を着ました。本当に着やすくてよく着てますね。薄くて軽くて涼しい上に牛首ですのでとても丈夫です。長襦袢は夏単衣のものが重宝ですが、半衿を洗うために外してしまっていたということもあって単衣のもので半衿は楊柳です。でも帯揚げは夏物。いいのか悪いのかよくわかりません。帯締めは三分紐で通年使っています。帯は軽い質感で単衣に良く合う感じです。帯留はきもの館で販売中のうさぎちゃんです。
こちらは夏牛首の帯です。これも単衣時期と夏に使えます。色合いがシックなので秋に向けていいのではないでしょうか。帯留はトンボ玉です。後ろにあるのは江戸時代のふとん地です。藍が全く褪せていないのに驚きます。
三日目はかがりの八寸帯です。この帯も色々な着物に合わせて着ています。帯合わせで思ったのですけど、着物は素材や色、柄が違いますが形が同じなのでコーディネートがしやすいのだと思います。お洋服だとスカートでも丈や形が様々で、合わせるシャツやセーター、ジャケットも形が様々で「色は合ってるけど丈が変」など組み合わせが難しいかもしれません。やっぱり着物はよくできています。
帯留は前日と同じトンボ玉の反対側です。後ろは火消し半纏です。音月桂さんの退団公演「仁」に出てくる江戸時代の火消し、「を組」の頭取、辰五郎親分を思い出しますね(オタク )。
今回三日間とも帯留をしてみましたが、お手伝いに来て頂いているアドバイザーの先生も素敵な帯留をされていましたのでご紹介いたします。
すごくインパクトのある帯留です!手作りのものだそうです。黒いところはオニキスだそうです。大きい!注目の的ですね!
こちらも大きめです。きれいな深いグリーンですが何か素材はわからないそうです。黒地の着物にビーズのついた帯締めにきらりと存在感があります。
こちらは一粒パールが美しい繊細な帯留です。フォーマルの着物でも合いますね。帯の水玉とリンクして涼しげです。
こちらもすっきりスマートな帯留です。ガラス細工のようです。すきっとした装いにお花の柄がほっこりとポイントになります。
着物の着こなしに帯留をプラスするとまた新たなお楽しみが増えます。またきもの館やあべのアポロ店にも新作の帯留を並べたいと思っていますので楽しみにしていてくださいね!