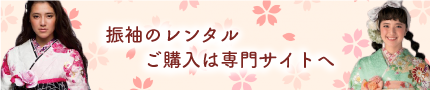blog
昔の婚礼衣装 裾引き黒振袖の着付け
2015年11月20日
みなさま、こんにちは!
ただ今本決算赤札感謝市まっただ中のきもの館でござます。
今回は前回の続きで、じないまち交流館の二階で行われましたじないまちキモノ散歩のメインイベント「昔の婚礼衣装 裾引き黒振袖の着付けライブ」のご紹介をいたします。
花嫁衣装と言えば白無垢です。「嫁ぎ先の色に染まる」という純白のきもの姿が思い出されますが、今回の花嫁衣装は黒い引き振袖の花嫁姿です。黒い色は「あなた以外の色には染まりません」という意味合いがあるのだそうです。近頃は引き振袖がお洒落で人気というのを耳にしたことがあります。今回は大正から昭和初期にかけての寺内町での婚礼の様子をビデオで見て頂き、その後実際に花嫁化粧、角隠しと引き振袖の着付けを解説をして頂きながら実演して頂きました。婚礼の日、家でお支度をした花嫁さんが正装をしたご親族と共に嫁ぎ先へ向かい結婚式を挙げる様子を寺内町で2年前に再現されています。
そうです。花嫁のご両親役は箱田さんご夫婦です。この動画で着付けをされている方が今回解説をして下さったのですが、実際に数年前に家で花嫁支度をして婚礼を挙げられたおうちがあったそうです。花嫁出発の頃にご近所の方が表に見送りに出て来られてお父様が皆さんにご挨拶をされたのだそうです。そしてその次に花嫁さんも「私が嫁いだ後は父と母のふたりになります。皆さまどうぞ父と母をよろしくお願いします。」とご挨拶されたそうです。地域ぐるみのお付き合いがうかがえる素敵なエピソードです。
さて、早速婚礼支度をご覧いただきましょう。日本髪をつけて水化粧されたお姿からスタートです。モデルは前回ご紹介しました通り箱田さんのお嬢さんです。司会は中林寝具店の中林さんです。
花嫁のお化粧も眉を短めに描くとか頬紅の入れ方とか決まりがあるそうです。数年前まで赤い口紅が流行らなかったので花嫁さんもピンクのものを使ったりしていたのだそうですが、最近は赤が復活ですので花嫁さんもきりりと赤い口紅です。やはり花嫁さんには赤い口紅が似合うと仰ってました。
日本髪にたくさんの簪をつけます。簪も関西と関東とではつけ方が違うのだそうです。関東は片側だけですっきりと、関西は左右対称に二つずつつけます。
まずこうがいをさして両方に飾りをつけます。
前に櫛をさします。
前にも飾りを。
後ろ挿し。
前飾りの簪は本当は角隠しをつけてから挿します。では次に角隠しをつけます。もうひとつ、綿帽子というのがあります。私は自分の結婚式には綿帽子だったのですがすっぽりとした形になった布を被った記憶があります。もともとは真綿を伸ばしたものを被っていたのだそうです。角隠しは眉が見えるか見えないかのラインで被り、前は富士山のように作るのがポイントなのだそうです。
そして前飾りの簪をつけます。
出来上がり。
続いて黒引き振袖の着付けです。赤い長襦袢に黒い振袖が映えます。お二人がかりで着付けていきます。
これは伊達締めではなく伊達巻きというそうです。ぐるぐるとかなり巻きつけます。
これは昔の丸帯だそうでものすごーく固いのだそうです。今の振袖の帯は柔らかくひだがたくさん細かく作れるのですが、これはそんなわけにもいかないず苦労して結んでくださっています。今回はシンプルな立て矢です。
そして赤いしごきを飾ります。筥迫も。七五三で見かけるのと同じですねー。
花嫁さん、完成です!
写真がピンボケで本当に申し訳ないです。
花嫁さんだけではもちろんいけません。花婿さん登場です。こちらの方は本当にモデルをされている方だそうで手足が長く、用意された紋付袴が少し短かったです。
新郎新婦の出来上がりです。涙が出そう。

素敵な新郎新婦さん!本当に特別な晴れの日です。お若いお二人の姿にじーんときます。
新郎新婦のお二人で寺内町を少し歩いてくださいました。新婦のご実家、大正絽漫の箱田さんの所まで歩きます。ご両親にお見せしなくちゃ!
花嫁の父と母の箱田さんご夫婦と。お父様、一足早くお嬢様の花嫁姿を見てしまいましたね。神妙な面持ちなのは涙をこらえているのでしょうか。
旧杉山家住宅まで行こうかというお話でしたが、あいにく雨が降ってきて断念。ちょうど雰囲気のピッタリな傘が大正絽漫さんにあってさして頂きました。絵になります!
家での婚礼というのは今ではなかなか難しいかもしれませんが、花嫁支度を家でするというのはとても素敵だなと思いました。娘でいる最後の日を慣れ親しんだ家で家族に囲まれながら嫁ぐ準備をする・・・。皆で正装になり、家族最後の時を過ごして式場に向かう・・・。想像するだけで本当に心に残る最高の一日になりそうです。またまた色々な妄想をして涙が出そうになりながらほんわか幸せ気分になりました。
毎回、忘れてしまいそうな日本の素敵な風習を思い出させてくれる寺内町のみなさま、本当にありがとうございました。