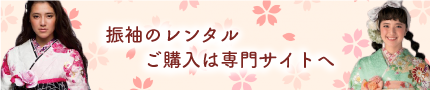blog
都・えん遊会での着物
2016年2月24日
みなさま、こんにちは!
四日間催されておりました「都・えん遊会」も雅やかな雰囲気の中、無事に終えることができました。会場には作家の先生、工房の素晴らしい作品が一堂に会し、大変見応えのある催しとなりました。先生、問屋さんの皆さま、本当にありがとうございました。
そして、可愛らしい舞妓さんも毎日先斗町から通って下さいました。踊りも披露して下さりお客さまも大変喜んでくださいました。本物の舞妓さんを見ることはほとんどないので、間近でお話できて私も嬉しかったです。京都で舞妓さんや芸妓さんの恰好をして写真を撮るお店があると聞いていましたが、今回初めて「私も舞妓さんの恰好をしてみたいわ」と思いました。かなりの年齢オーバーですけど機会があればしてみようかな・・・。こちらは先斗町の市照ちゃんです。素敵な舞いをありがとうございました。 
さて、今回は「展示会での着物」編です。二枚の着物と帯で四日間を着まわしてみました。 初日は結城紬に染の名古屋帯です。半衿もモスグリーンでオールグリーンになってしまいました。せめて帯揚げだけクリーム色にして明るさをプラス。帯締めは小田巻の飾りのついたものをしてみました。 

二日目は着物を小紋に替えました。後は同じです。あ、帯揚げをモスグリーンにしてみました。ポイント柄の名古屋帯は柄をちょうどいいところに出すのが難しいと敬遠される方もいらっしゃいますが、季節感やストーリー性が感じられるものが多くて楽しいです。あまりど真ん中にお柄が来ないようにだけ気をつけます。この半衿は麻の葉の刺繍がしてあってお気に入りなのですが、池本部長に「マスクメロンみたいやな。」と言われてからマスクメロンに見えてしかたありません。 

三日目は結城紬に安治郎先生の染めの名古屋帯です。半衿は絞りのからし色のものを合わせてみました。小物類も同じで。半衿は毎日付け替えるのは手間なので長襦袢を数枚、色々な半衿をつけて用意しておきます。本田さんはささっと15分で半衿付けができるそうですが私は異様に時間がかかります。なんでかな・・・。 

最終日は小紋に安治郎先生の名古屋帯で。合っているのかどうか良くわかりません。普段着の紬や小紋は気持ちも楽でどんな組み合わせをしても「まぁ、いいか」と楽しく着られます。こういう時は着付けもあまりきっちりしなくてもいいんじゃないかと思います。と言っても私は仕事着ですので気楽過ぎたらいけませんね。すいません。でも楽しく着物を着ています。あ、帯締めの小田巻が二つになっているのにお気づきでしょうか。紫のものがほどけてしまって使えなくなってしまいました。二つでもぽちっと可愛いですね。舞妓さんも大きな帯留をされています。帯締めも三倍ぐらいの太さです。とても高価な帯留だそうで「ぽっちり」と呼ぶのだそうです。また舞妓さんを見る機会があれば帯周りに注目してみてくださいね。 

これから春に向かって着物ライフが一番楽しい季節ではないでしょうか。それに卒業・入学シーズンでフォーマルの着物を着る機会も増える時期です。フォーマルのお席は立場を考えて着物を選ばなければいけませんが、お楽しみの着物はお好きなものを選んで自由に楽しく着て頂けたらなと思います。着付けもそれほど難しいものではありませんし、知っておくと着崩れた時も自分で直せるので安心です。本きもの松葉でも着付け教室(あべのアポロ店の着付け教室←コチラ)をしておりますのでぜひ気楽にチャレンジしてみてくださいね!