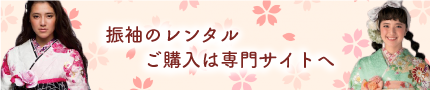blog
南国まつりでの着物
2016年8月10日
みなさま、こんにちは!
毎日毎日暑いですね。この暑い中催されました南国まつりにお越しいただきましたお客様、誠にありがとうございました。今回は大島紬だけではなく、沖縄県の無形文化財であります琉球びんがたの作品も揃えられ、琉球染織の新川先生が沖縄のお話と三線を弾きながら島唄を披露してくださいました。沖縄の方の長寿の秘訣は「笑う」ことだそうで、苦しい時ほど大笑いするといいというお話に「なるほど」と深く頷いてしまいました。そして会場の皆さんと一緒に大笑いをしました。本当に気持ちがすっきりして元気が出てくるので不思議です!
新川先生と市原亀之助商店の田中さんと。
琉球紅型ができたのは琉球王朝の繁栄した14~15世紀ごろで、その頃は「形付け」と呼ばれていて「びんがた」という呼び名は明治に入ってからだそうで、漢字の「紅型」が普及しだしたのは昭和に入ってからだそうです。顔料を使った色鮮やかなびんがたは型を使った型染で柄が細かいほど高価になります。型紙や糊ふせをした作業工程の作品も見せて頂き、さらに紅型の素晴らしさを感じることができました。新川先生、四日間ありがとうございました。
さて、今回は「展示会での着物」編です。四日間でしたので2枚の着物を帯を変えて着てみました。もう何年も着ている着物ですので今回は気分を変えるために帯留めをしてみました。
初日は夏大島紬に玄才先生の夏の名古屋帯です。黄色にピンクという可愛い色合いで攻めてみました。帯留めはガラスに色々な色の布が入った涼し気なもので夏用として使っています。
二日目は越後上布に夏牛首の洒落帯です。上布は麻のことです。やはり涼しいです。帯留めは牛角でできたトンボの帯留めをしました。トンボは秋のイメージなのか夏物の着物や帯によく見かけるモチーフです。前にしか進まず後戻りしないというトンボの習性から縁起物のお柄でもあります。
三日目は夏大島紬に麻の栗山紅型の名古屋帯です。紅型でも今回の琉球紅型は本紅型とも呼ばれ、工程や顔料を使うことなど独特のものです。他に京紅型、江戸紅型があり、栗山工房は京紅型です。ともに顔料ではなく染料が使われ、型紙を使うものの本紅型とは違った工程で作られます。帯留めは昨日と同じトンボのもの。お花の中のトンボになりました。
そして四日目は越後上布に羅の帯です。帯留めはよーく見ると猫ちゃんなのです。七宝焼きのもので、先日、帯留めを数種類仕入れてきました。 これはそれなりの大きさがありますが、三分紐にちょこっとついてるサイズの小ぶりな帯留めをずっと探していて、可愛いものが見つかりましたので楽しみにしていてくださいね。
売り場には夏物の刺繍の半衿だけ先に置いています。帯留めはもうしばらくお待ちください。
これはガーゼ素材の刺繍の半衿です。気持ちよさそうです。
こちらはシルックの刺繍の半衿です。
こちらもシルックでストーンがついたものです。
展示会中、朝から猫(二匹飼っています)が布団の上で毛玉を吐いてしまい、忙しいのにシーツとマットを洗う羽目になって、時間的に着物を着てから洗濯物を干さなければいけなくなってどうしようかと思いましたが、よく考えるともともと日本人は着物を着て家事をしていたのだから当たり前かとやってみると別にいつもどおりでした。これからも「着物だから」と構えるのではなく自然に着物を着られるようになろうと思いました。
本日から日曜日まで、富田林本店はお盆休みをいただいています。きもの館は本日はお休みですが、11日からお盆にかかわらず通常通り営業しております。ショッピングセンターのお店も毎日営業しております。きもの館では11日から15日まで、「高校生浴衣プレゼントキャンペーン」の第二弾(←コチラ)を催しております。前回大好評でしたので、来られなかったお嬢さんはぜひこのチャンスにきもの館へ浴衣を選びに来てくださいね!