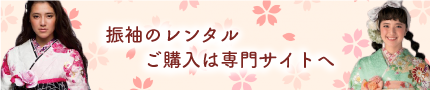blog
べっぴんの会2017での着物
2017年6月21日
みなさま、こんにちは!
きもの館で四日間催されましたべっぴんの会へお越しいただきましたお客様、誠にありがとございました。
普段の展示会ではなかなか並ばない本加賀友禅やクロコのバッグなど、特別な商品を堪能して頂けた展示会でした。ご参加くださった作家の先生、問屋さんの皆さまお世話になりまして誠にありがとうございました。
今回は恒例の「展示会での着物」編です。今日は大雨ですが、期間中は梅雨入りのニュースにもかかわらず晴れ続きでとっても良いお天気で助かりました。四日間ですので二枚の着物を帯を変えて着てみました。
初日はしょうざん生紬に和紙が織り込まれたかがり帯を合わせました。辻が花が描かれたこの生紬の着物はお気に入りで単衣の時期に着るのをとても楽しみにしています。この和紙の帯も無地ですが微妙に色々な色が混じっていて合わせやすく重宝しています。この日は透かし彫りの帯留めを合わせてみました。


2日目は丹波布の着物に同じく和紙の帯を合わせました。以前にもご紹介しましたこの丹波布は丹波に自生する植物で染められた綿と絹を混ぜて織られた織物で、今は趣味的に生産されているぐらいのとても珍しい織物なのだそうです。私も義母から譲り受けた着物で大事に着たいなと思います。なんか全身写真がピンボケになってしまいましたが、ピンボケぐらいの方がいいなと思っているところです。


三日目はしょうざん生紬に大久保玄才先生の絽の染帯です。このコーディネートは毎年お決まりになっています。ピンクを合わせると華やかさが出ますね。帯締めにキリリとブルーを入れてみました。数年前は帯締め帯揚げは薄いピンクを合わせていたようです。ブログを遡ると「あー、〇年前はこんな組み合わせで着てたんだ~」と、自分の備忘録にもなっているきものガーデンです。


最終日は丹波布に栗山工房の和染紅型の麻の帯を合わせました。同系色で初めての組み合わせです。先日のバスツアーのお客様が格子柄の紬にお花のお柄の帯を合わせてらっしゃったので真似してみました。いかがでしょうか。私は気に入りました。栗山工房さんは昨年工房見学に行かせていただき、先日のファッションカンタータでステージも拝見したのでこの帯を締めると色々な情景が思い浮かびます。伝統工芸の着物や帯を身につける喜びとはこういう気持ちなのだなぁと思います。産地の方々は代々受け継いできている歴史や思い出、そして色々な思いがあるからこそ、大変な思いをしても後に引き継いでいきたいと努力されているのかもしれません。


きもの館では明日から「きもの何でも無料相談会」(←コチラ)を催します。タンスから出してみるとカビが生えていたり何かわからないシミが浮き出ていたりということはよくあります。また、どなたかに譲りたいのだけれど仕立て替えはできるのかな、この帯はどんな着物に合わせたらいいのかな、などなど、着物に関するご相談を無料で承ります!
明日から土曜日までの三日間、京都から専門の悉皆屋さんも来られます。この機会におうちにある着物を見直してみてはいかがでしょうか。