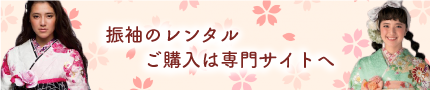blog
べっぴんの会2019での着物
2019年6月19日
みなさま、こんにちは!
四日間催されましたべっぴんの会にお越しいただきましたお客様、誠にありがとうございました。
そして、ご来場頂きました日本の名工・金彩友禅を生み出されました和田光正先生には四日間毎日、講演会で興味深いお話を頂きまして本当にありがとうございました。先生の作り出された素晴らしい作品を一つ一つ解説していただき、一つ一つに込められた思いや図案の謂れをお聞きして、さらに金彩友禅の魅力に深く触れることができました。先生の「この道65年」の記念の展示会でしたが全くお歳を感じることはなく、まだまだ溢れる創作意欲をお持ちで、ご自身の作られた作品を楽しそうに嬉しそうに語るお姿は、失礼ながらまるで少年のようだなと思うほどでした。これからも私たちを魅了するたくさんの作品を作っていただきたいです。先生、四日間本当にありがとうございました。
さて、今回は「展示会での着物」編です。
四日間を二枚の着物で帯を替えて着てみました。
初日は絹芭蕉の着物に塩瀬の夏帯です。すすきの柄の絹芭蕉は一方付けの小紋です。帯のつゆ草の青い色が印象的で、他にもフジバカマかな?野の草花が描かれて涼し気な印象です。帯締めをもう少しだけ優しい色を合わせたかったのですが持ち合わせがなく少し濃い色になってしまいました。
和田先生の作品、色打掛の前で。千代の富士のお嬢様が結婚式に着用されたものだそうです。先生は千代の富士関の化粧まわしを作ってらっしゃいました。



2日目は夏大島に刺繍の帯を合わせました。こちらも刺繍の青い色が印象的です。先日のファッションカンタータで、今年は水色が流行っているとお聞きしました。そのせいなのか綺麗な水色の着物をよく見かけます。夏に向けて爽やかでピッタリです。



三日目は初日の一方付けの小紋に夏牛首の袋帯を合わせました。初日の帯のときははんなりした雰囲気のコーデでしたが、この帯だと少しシックできりっとしたコーデになったように思います。顔はにやけてますが。
後ろの訪問着は和田先生の作品集の図録の表紙になっているものです。とても手の込んだ実に見事な逸品でした。



四日目は二日目の夏大島に先日のファッションカンタータでも締めていた栗山紅型の麻の夏帯です。黄色の帯を合すと着物の黄色いところが浮き立って二日目とちょっと違う色に見えますね。他のものでも組み合わせる着物や帯の色が影響しあって違う色の印象になったりすることはよくあります。面白いですね。



一応6月は単衣の時期ですが気温によってはもう夏物も着始める時期です。今回の着物は単衣時期から盛夏も着られる着物です。軽やかで薄い着物に袖を通すとほんとに気持ちいいです。
帯周りが重なってはいますが、しゃりっとした生地は肌に張り付かず風を通すので意外にお洋服より快適だと思います。布が身体を覆うので暑い太陽光線からも冷房の冷たさからもカバーされます。またファッションカンタータの話になりますが、前夜祭のパーティーで渡辺大さんが着物について「暑さ、寒さに柔軟に対応できて今の気候に合っている」と仰っていました。暑いと思って薄着で出かけたら冷房がききすぎて寒かったということがよくありますが着物だと程よく調節されます。普段着物を着ている方でも夏は着物を着ないと仰る方はぜひとも夏こそ着物を着てほしいと思います。
今年は例年より暑さがましなように感じます。大阪の梅雨入りはこれからでしょうか。年々気候が変わってよくわからなくなってきます。ちょうど昨年の今頃、大阪に大きな地震がありましたが、昨日も新潟県、山形県で大きな地震が起こりました。災害に合われました方々には心よりお見舞い申し上げます。