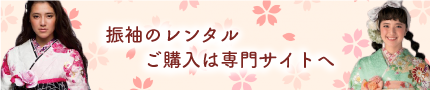blog
2022年都えん遊会での着物
2022年2月22日
みなさま、こんにちは!
平安の雅な世界・都えん遊会にお越しいただきました皆様、誠にありがとうございました。
三日間、西陣和装学院学長でいらっしゃいます毛利ゆき子先生にお越しいただき、様々なお話を交えながら十二単衣の着付けを披露していただきました。
「十二単衣」という呼び名は後世の言い方で、正しくは「唐衣裳姿(からぎぬもすがた)」と言い、着付けのことは「衣紋」というそうで、「十二単衣の着付け」の本来の言い方は「唐衣裳姿の衣紋」というのだそうです。ゆき子先生のはんなりとした語り口で平安の装束のこと、宮中でのこと、現代まで続く日本の儀式のことを聞きながら、気持ちはすっかり平安時代へタイムスリップです。
装束の準備をしていらっしゃるゆき子先生です。伝統文化研究家としての活動もしていらっしゃって、20年ほど前にも先生に十二単衣の着付けショーをして頂いたことがあります。着物の創作もされていて「ゆきこコレクション」としてきもの館にもいらしてくださっています。ご子息様は「安治郎」として弊社でも人気の着物作家でいらっしゃいます。

三日間で9回も着付けをして下さいました。まずは小袖と長袴、鬘をつけてお姫様の登場です。今回着付けモデルを募集いたしまして、厳正なる抽選(店長たちのじゃんけん)の結果、9名のお姫様を選ばせていただきました。これからご紹介する写真はまぜこぜですので途中でお顔が代わっても驚かないでくださいね。

鮮やかな若草色の単を着た後にグラデーションが美しい五ツ衣を重ねます。

そして光沢のある打衣(うちき)を重ね

豪華な表着(うわぎ)の上にお袖巾が短い唐衣をつけます。そして腰から下に白い裳をつけます。

胸元にはお砧紙、手元には檜扇を持ちます。

完成です。

後ろ姿です。

横から見ても美しい。

着付けをする人を衣紋者というそうで前と後ろと二人で衣紋をします。前衣紋者は立ってはいけないそうです。衣紋者を務められましたゆき子先生と山口先生の所作がとても美しく、これこそ日本の美だなと思わされました。装束をつけたお姫様たちも神々しくて眼福。
ゆき子先生の様々なお話も興味深く、知らなかったお話ばかりでとても充実した三日間でした。
ゆき子先生、山口先生、本当にありがとうございました。
そんな今回は「展示会での着物」編でございまして、平安のお姫様の後にご紹介するのもほんとに気が引けますがちょっとだけ。
今回は都えん遊会に遊び心の会も開催していまして、合計6日間の展示会でございました。私は都えん遊会の前日から四日間、着物を着ましたのでその時の着物をご紹介いたします。
初日は少しいつもと違う感じにしたくて黒い半衿をつけた黒の長襦袢で結城紬を着てみました。ストーンがついてきらりと光る半衿とビーズのついた中村玉緒さんの袋帯とで、しっくりした結城紬が少しモダンな雰囲気になったのではないでしょうか。



都えん遊会でははんなりした感じにしたくて優しい色の結城紬で。帯は毎年恒例のお雛さんの帯です。この半衿が白地ではなく少しクリームがかっていてさらに優しい感じになります。



こちらも結城紬にお雛様の帯です。帯の前柄が前日と違っています。反対巻きにすると別の柄が出るようになっているのですが、反対に巻くのは意外に難しいのです。アドバイザーさんに秘策を教えてもらってやってみました。たぶん見た目ではちゃんと巻かれてますよね!



そして鶸色の結城紬に安治郎先生の名古屋帯を。はんなりから少しシャープな印象になりました。今回ぜひとも言い訳したいのが、花粉症で目が腫れているのと、今年に入って一回も美容院に行けてなくて髪がどうにもこうにも収まらなかったということです。あしからず。



着物は着るのも見るのも楽しいものです。
きもの披露空間(←コチラ)でも皆さんの様々に素敵な着姿をご覧いただけます。
そして着物のおしゃれに気軽に取り入れられる半衿や帯留めなど、着物好きな方に喜んでいただけるような品揃えを意識した新ショップが泉大津にオープンしています。
場所は南海本線泉大津駅に直結のいずみおおつCITYにございます泉大津店です。
着物の愛好家という意味で「freak」、自由に着物を楽しんでもらいたいという意味で「free」を組み合わせた「kimono freek キモノフリーク」というショップ名にしました。

また店内の様子をブログでご紹介したいと思っています。
京都の小物屋さんでスタッフと一緒に私も色々と商品を選びに行って参りました。是非見に来てくださいね。