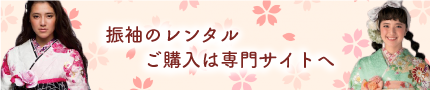blog
玉鬘神社創祀での能奉納
2018年11月24日
みなさま、こんにちは!
空気の冷たさに冬の訪れを感じるようになってまいりました。夜空も澄んでいて月や星が綺麗に見えます。好きな季節です。
そんな中、いつもお世話になっておりますご婦人が「能を見に行きませんか」とお誘いくださいました。もちろん能ビギナーの私ですのでご婦人となら心強いと思いご一緒させていただきました。
この度は新しく作られる神社での奉納舞としての能だそうで、わからないことだらけでしたが行ってみるととても清々しく心が洗われるようでとても素敵なひと時を過ごすことができました。
場所は奈良の初瀬(はせ)で、万葉集で「隠国(こもりく)の初瀬」と詠まれている地です。「こもりく饅頭」が売られていたのはこれにちなんでいるのかと後でわかりました。ここは神の籠もる霊地で與喜山の與喜天満神社から緑の苔の連歌道と言われる古道を行くと長谷寺へ続きます。その周辺には大国主命の娘を御祭神とする延喜式内社鍋倉神社跡、源氏物語で語られる夕顔の娘、玉鬘にちなむ玉鬘庵、その奥に素戔雄(すさのお)神社があり大銀杏のご神木がそびえています。この初瀬の地は古代日本の聖地であり、神仏習合の聖地であり、源氏物語の舞台であり、法学連歌も行われるなど様々に特別な地なのだそうです。
その玉鬘庵は明治の初頭に無くなり本尊の観音坐像は長谷寺に安置されていて、鍋倉神社は素戔雄神社に合祀されていたのを、この度鍋倉神社の再建と玉鬘庵跡地に玉鬘神社を建立する運びとなったそうです。
色々と説明を読むと面白く、もっと知識があったらなと思います。平安時代に長谷寺参詣が盛んだったそうで、源氏物語だけでなく蜻蛉日記や枕草子、更級日記にも長谷詣のことが書かれているのだそうです。
富田林からも近い奈良でこんなに有名人たちがお参りしていたとは興奮します。奈良の桜井周辺はお寺や神社が本当に多いです。
長谷寺の入り口で。今回はお参りせず、入り口だけです。


お天気が怪しかったのですが、雨ゴートではなく道中着で。安治郎先生のぼかしのコートで、紫式部にちなんで紫を(なんちゃって)。着物は神社の奉納なので柔らか物の方がいいのではとご婦人が教えて下さったので飛び柄の小紋です。ご婦人はこの季節のお柄の訪問着をお召しでした。
長谷寺の周りはお店が連なりウキウキします。


長谷寺側からの眺め。

草餅も美味しそう。ヨモギを入れて、本当に杵と臼でついています。

三輪そうめんの産地なのでにゅう麺が食べられます。絶対食べたいですやん。お昼は手作りゴマ豆腐もついたにゅう麺定食を頂きました。美味。

玉鬘神社を探して歩いていると、わー大きな木が見えます。あれがご神木の大銀杏の木です。

玉鬘神社ののぼりが見えてきました。

この階段を上がったところのようです。

もう人が集まっています。早めに来たので椅子に座ることができました。

すぐ横にご神木が。大きい!素戔雄神社です。

こちらが玉鬘神社になるところで、今日は舞台が作られています。

横に長谷寺が望まれ絶景です。すごく気持ちよかったです。

演目は「翁」と「玉鬘」です。
「翁」はきっとおめでたいときのものだろうと思って調べてみると、まさに別格の一曲で神聖な儀式であり、演者は神となって天下泰平、国土安穏を祈祷する舞いなのだそうです。能が始まる直前に雨が降ってきてしまったのですがそのまま屋外で決行。傘をさしながらでしたがこの景色の中で、静寂の中で、笛や鼓の音が響いて本当に身体が洗われるようなとても気持ちのいい空間でした。
もう一つ「玉鬘」はもちろん源氏物語の玉鬘で、その中の狂言を茂山逸平さんが演じられてらっしゃいました。ものすごく聞き取りやすかったのは何でなんでしょう。
能を見に行ったことはないのですが、大きな能舞台のある劇場で見るのと、今回のような奉納舞とはまた趣が違うのかもしれません。でも今回お誘いいただいて、初めての能が屋外で良かったなと思いました。雨なのに本当に気持ちがよく、ひょっとするとこの地が神聖な地でいい空気が流れているからかもしれませんが身体の中からきれいになるような気持ちがしました。
とてもいい体験をさせて頂いて、お誘いいただいて本当にありがとうございました。